学びの質は休み方で変わる

──集中力とモチベーションを高める、夏の学習戦略──
いよいよ8月に入り、夏期講習も佳境を迎えています。中学3年生にとっては、受験に向けた本格的な準備期間。8月2日(土)には進研模試の予行練習である「プレ模試」が実施されましたが、結果はいかがだったでしょうか。思った以上に手応えを感じた人もいれば、努力しているのに成果が出ず、焦りを感じた人もいるかもしれません。
実は、指導する先生たちも毎年この時期はドキドキしています。プレ模試の結果を見て、後半戦の指導方針を練り直すのが恒例。模試の結果が振るわなかった生徒やクラスが、本番で大きく伸びることも珍しくありません。だからこそ、今このタイミングで「どう学ぶか」「どう休むか」を見直すことが、秋以降の成績に直結します。
8月10日〜12日には夏期合宿も控えています。9月からは学校の実力テストや定期テスト、進研模試や五ツ木模試などが目白押し。これらの結果が、受験校の選定に大きく影響することを考えると、夏はまさに“勝負の季節”です。
しかし、がむしゃらに頑張るだけでは、モチベーションも集中力も長続きしません。むしろ、コンスタントに高い集中力を維持するためには、「休む」ことが極めて重要です。今回は、私自身が長年仕事の現場で実践してきた「休み方の工夫」を、受験生の皆さんにもぜひ取り入れてほしいと思い、紹介します。
① 25分勉強して5分休む「集中サイクル」
私が日々の仕事で取り入れているのが、ストップウォッチを使った時間管理法です。30分のうち25分間集中して作業し、残りの5分は必ず休憩を取る。これを繰り返すことで、集中力を高く保ち続けることができます。
勉強も同じです。最初のとっかかりがしんどいと感じる人は多いでしょう。でも「とりあえず25分だけ」と決めてタイマーをスタートすると、不思議と集中できてしまう。気づけばノッてきて、もっと続けたいと思う頃にアラームが鳴る。ここで心を鬼にして、いったん勉強を止めて5分休憩を取る。机から離れる、自習室なら伏せて少し目を閉じる。これだけで、次の取り掛かりが驚くほどスムーズになり、集中力がさらに高まります。
このサイクルを3〜4本繰り返したら、10〜20分の長めの休憩を入れるルールにすると、休憩が楽しみになって集中力が持続します。
この方法には副産物が2つあります。1つ目は、毎回時間を計ることで、自分が25分でどれくらいの学習量をこなせるかが見えてくること。慣れてくると「25分でここまでやろう」とタイムプレッシャーをかけて学習できるようになります。これは、受験直前期の過去問演習などで非常に役立ちます。
2つ目は、タイマーを押すことで脳が自動的に“勉強モード”に切り替わるようになること。これは本当に便利です。勉強を始めるまでの「気持ちの準備」が不要になり、スイッチが入るまでの時間が短縮されます。
② 週末にしっかり休む「楽しみの設計」
夏期講習がどれだけ大変でも、「楽しみ」を作ることはとても大切です。受験生だからといって、遊んではいけないわけではありません。むしろ、メリハリをつけることで、平日の学習効率が上がります。
例えば、日曜日のお昼は「これをして遊ぶ」と決めておく。ゴロゴロしてスマホを見るでも、お菓子を食べながらマンガを読むでも、家族とちょっと出かけるでもいい。その楽しみを目指して、月〜土を頑張るようにする。できれば月曜日に、週の学習内容を箇条書きにして、「終わったらこれして遊ぶ」とセットにすると最高です。
私自身も仕事でこの方法を何年も続けています。日曜に遊ぶために、平日で仕事をやり切る。最近では、金曜に余裕を持ちたいので、月・火でスタートダッシュをかける作戦まで立てています。
③ 「面白がる」気持ちを持つ
こうした工夫を紹介すると、「やってみよう」と動く人と、「分かってはいるけど…」と動かない人に分かれます。ここで大切なのが、「なんでも面白がる」気持ちです。
みんなは受験生。夏に頑張れば、2学期の実力テストで成果が出て、受験に圧倒的に有利になります。やらなければならないのは分かっている。だったら、ブツブツ文句を言わずに、いっちょ「面白がってみる」。休み方を工夫して、自分なりに実験してみる。そうやって、勉強そのものを“自分のもの”にしていく。
この「面白がる」精神は、勉強だけでなく、人生のあらゆる場面で役立ちます。受験も含めて、世の中の出来事に善し悪しはありません。それをどう捉えるかがすべてです。
嫌な勉強も、受験も、面白がってみる。
自分の工夫で、学びを変えてみる。
その姿勢こそが、成績を伸ばす一番の秘訣です。
夏期講習も受験勉強もまだまだ続きますが、みんなにとって高校受験に取り組める時は「今」この時しかありません。みんなの頑張りは、来年には必ず素敵な思い出に変わります。みんなで「面白がって」この受験を乗り越えよう! <塾長 高木秀章>







.jpg)
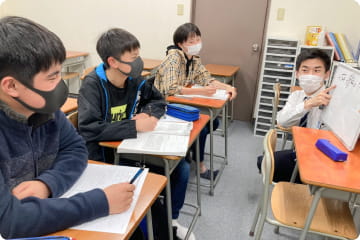
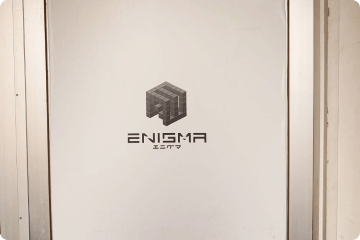
















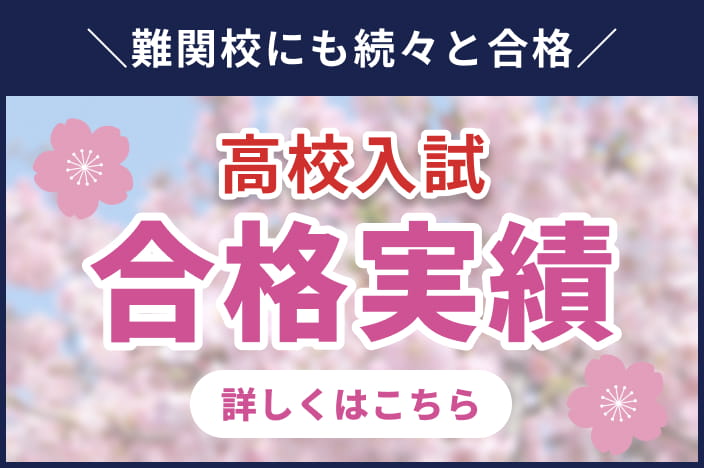
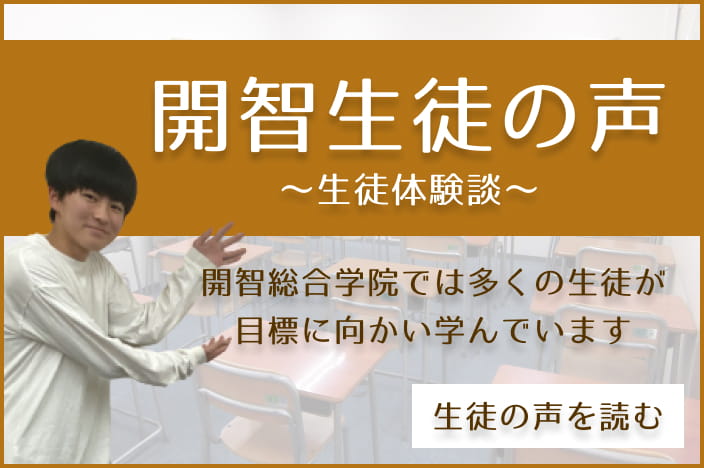
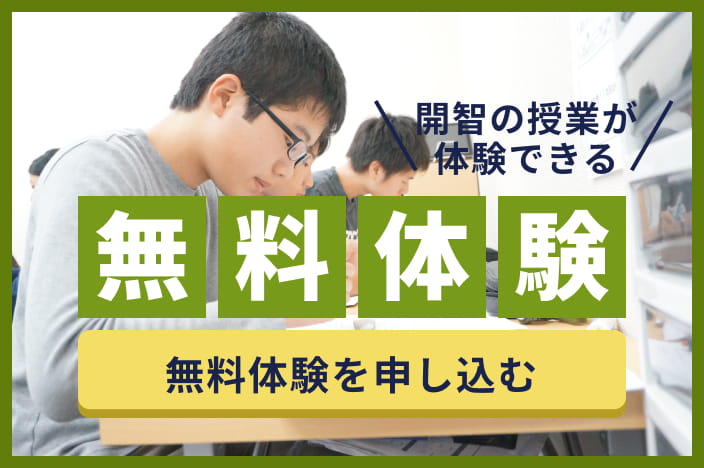




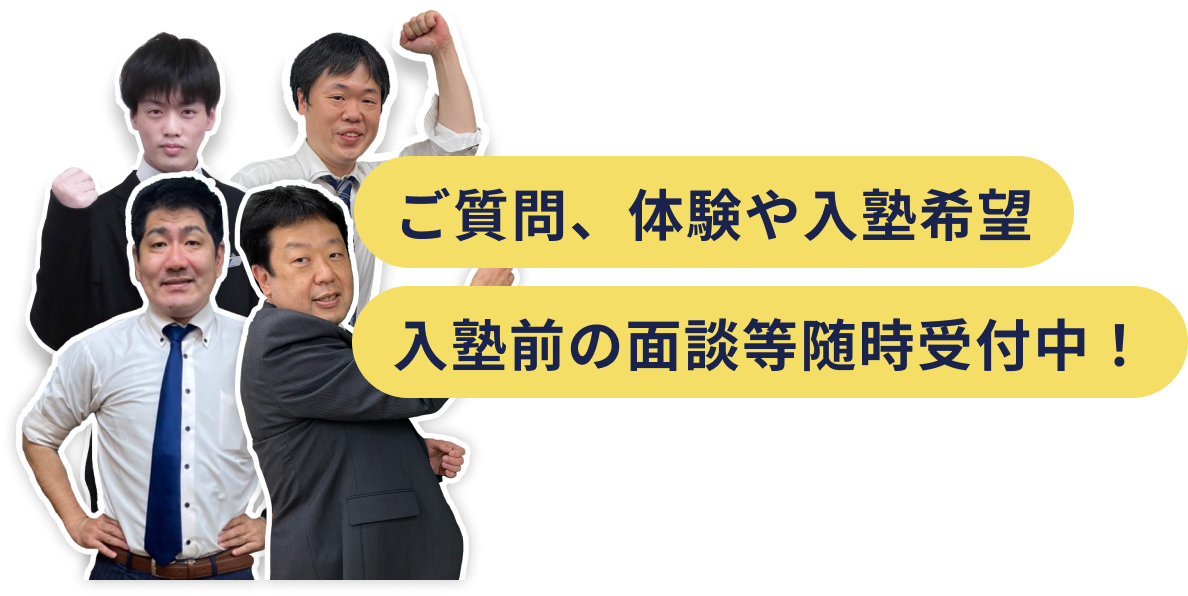
 電話する
電話する
 無料体験申込み
無料体験申込み
 チャットで相談
チャットで相談